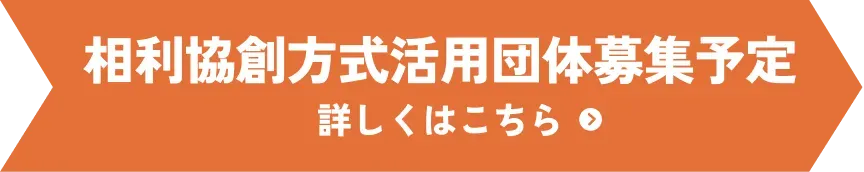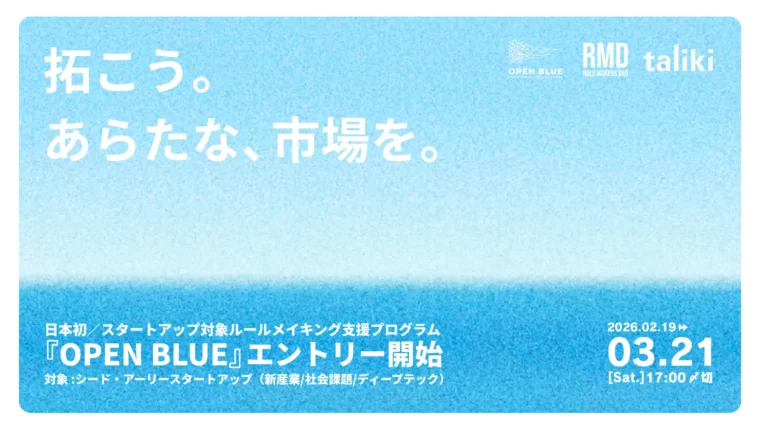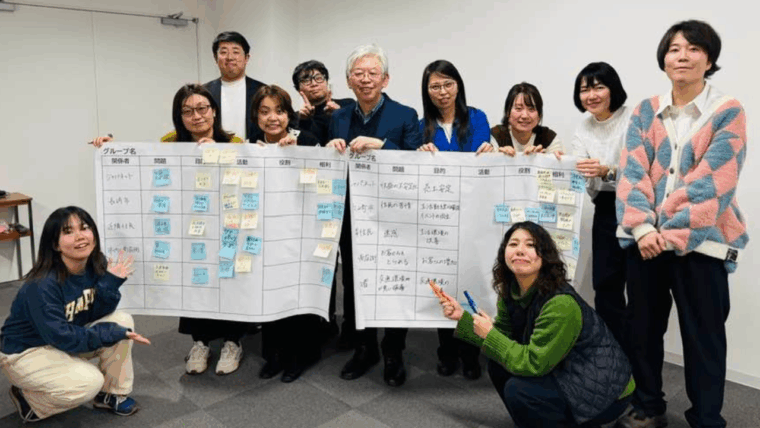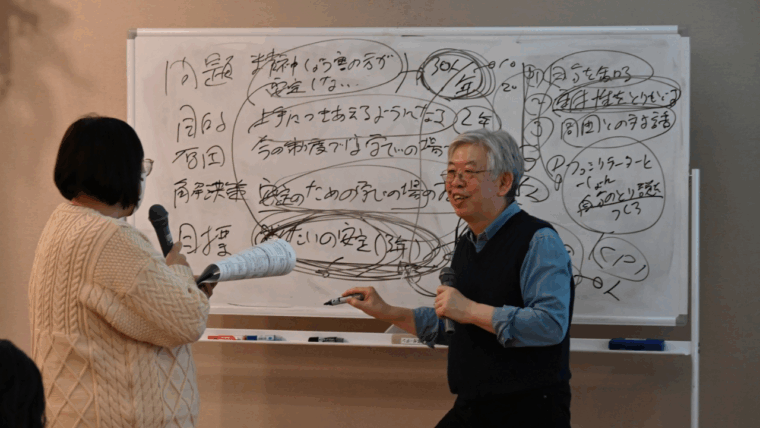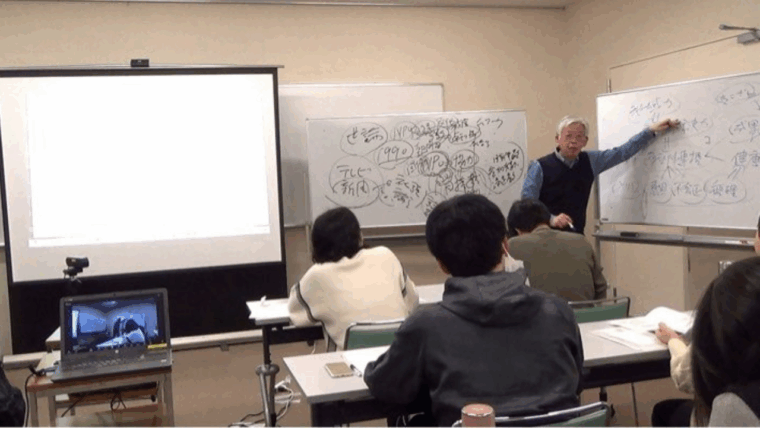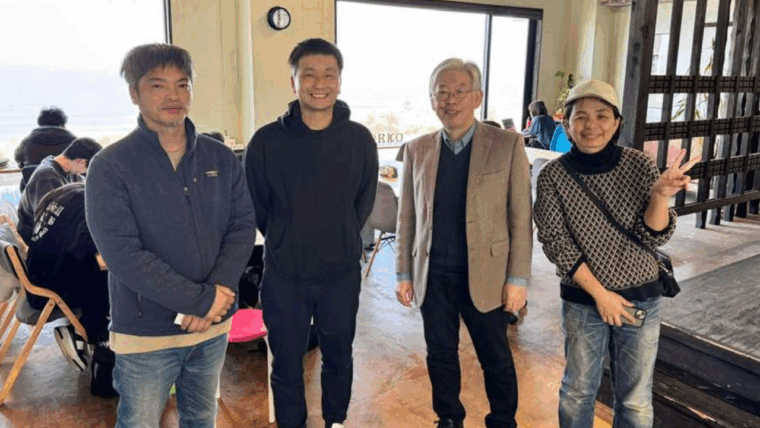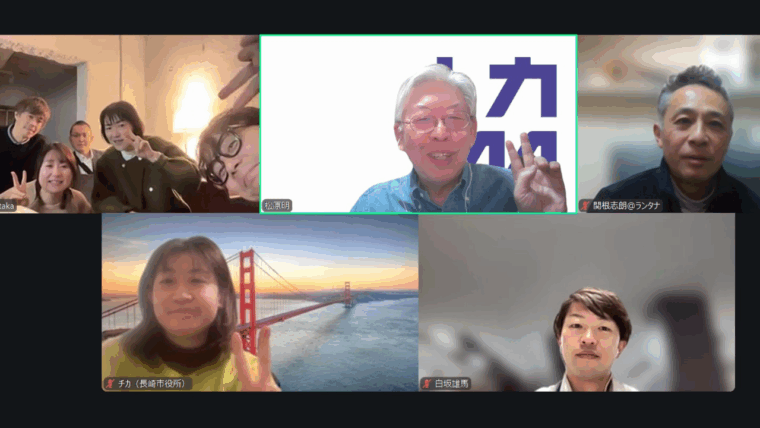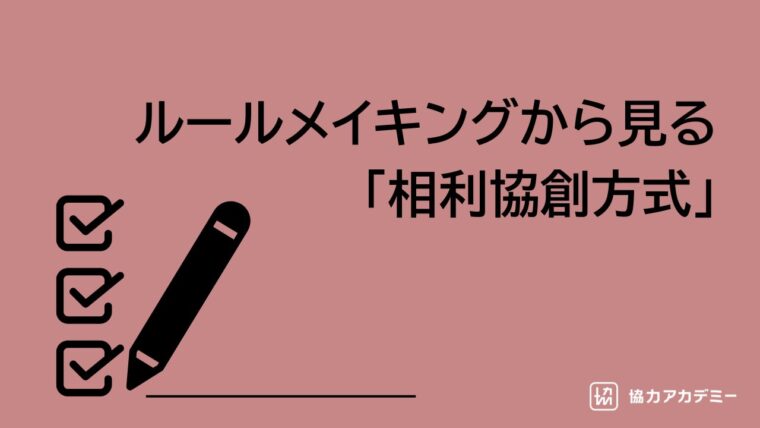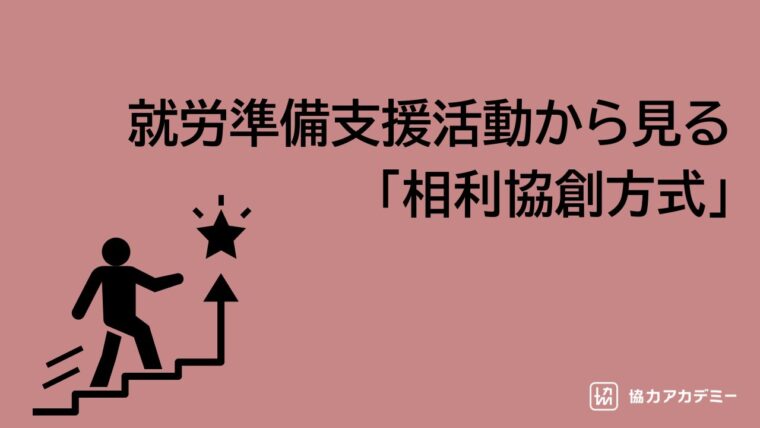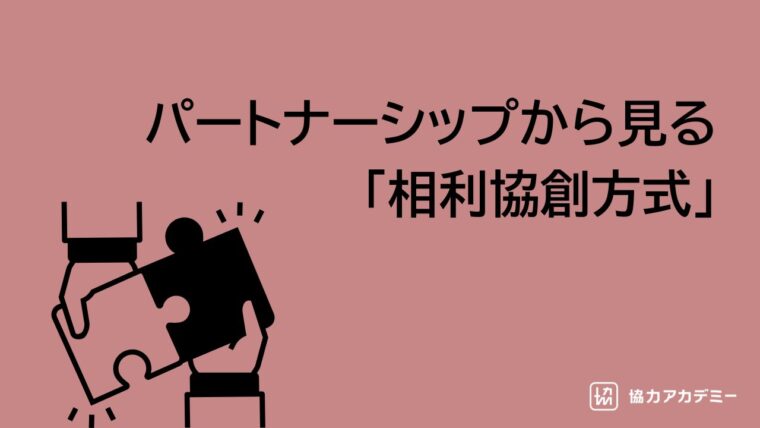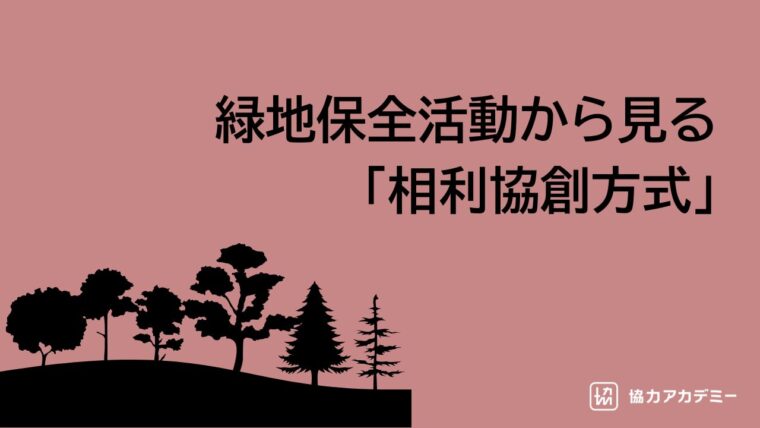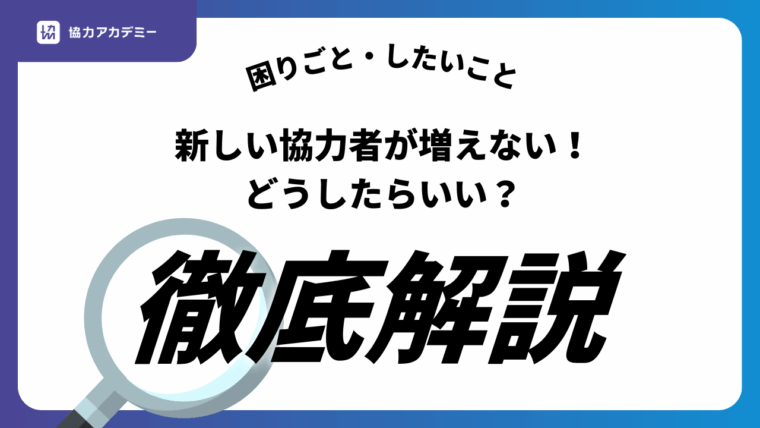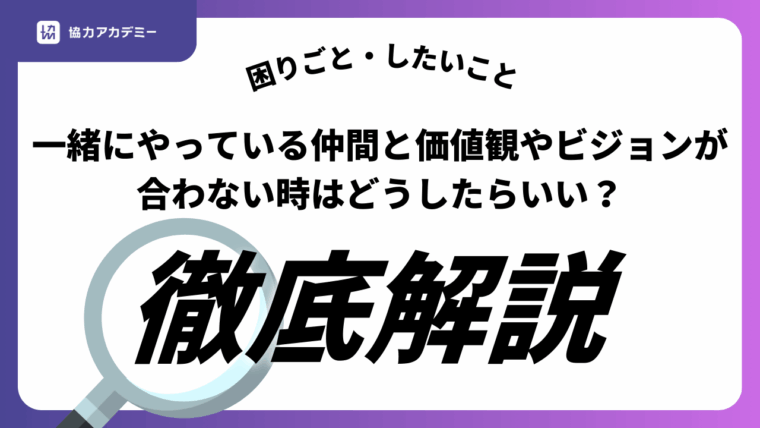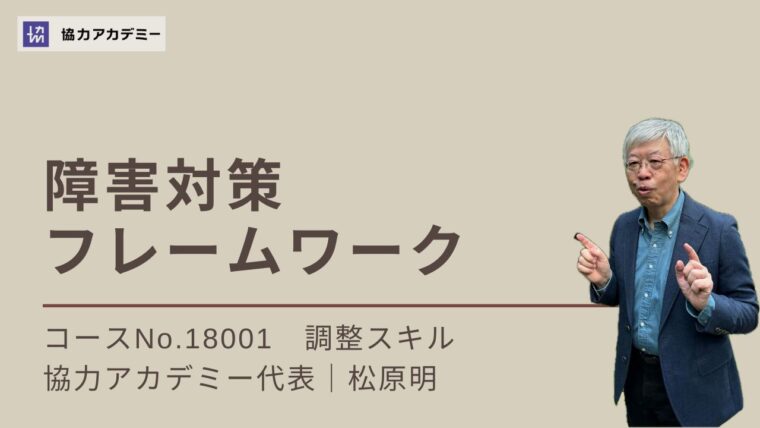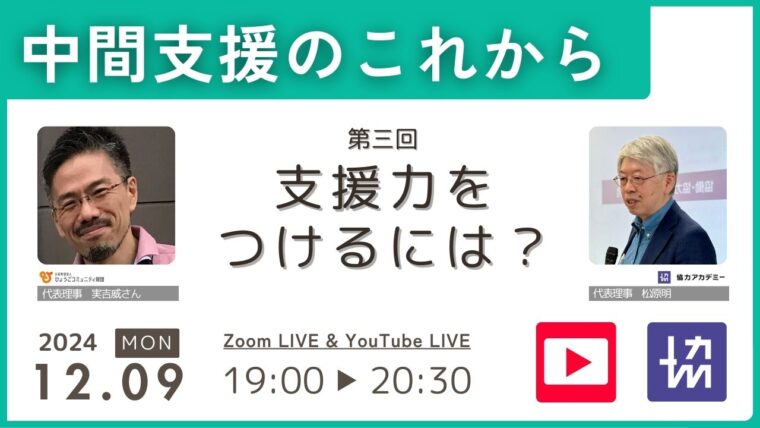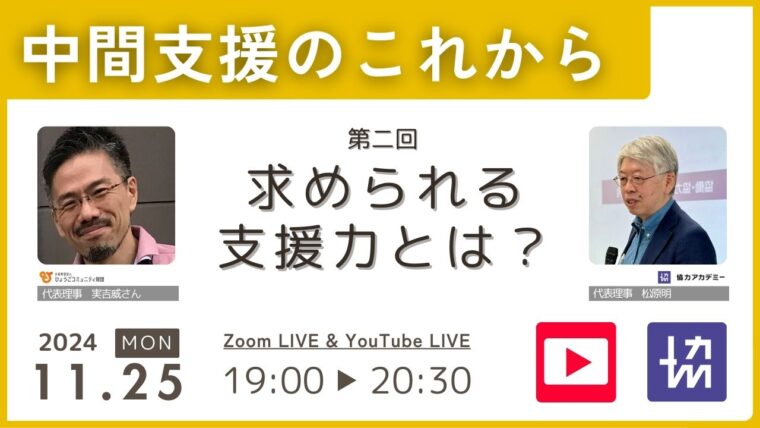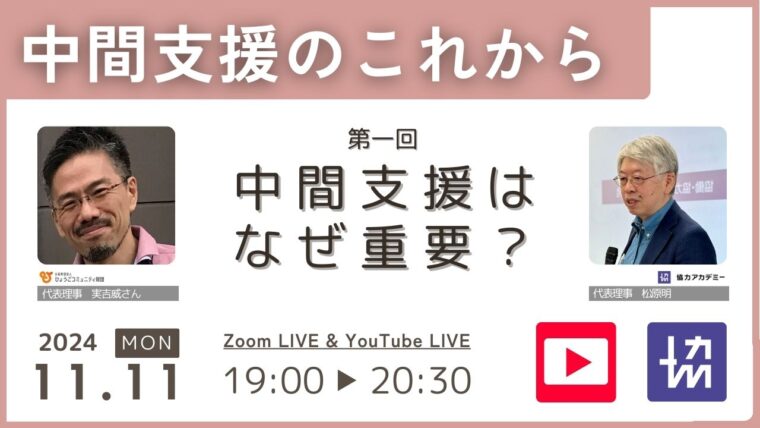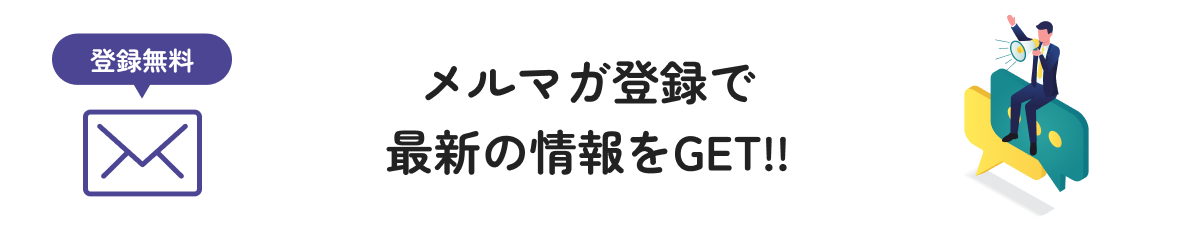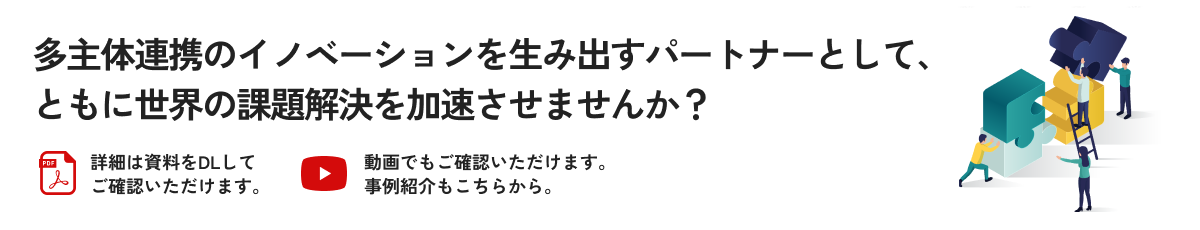TOOLS 相利協創の道具たち
TALK SESSION 相利協創を深く知るライブ&アーカイブ
NEW TOPICS 新着情報
SUBSCRIPTION 料金表
\ 今だけ30日間お試し無料! /
「伴走重視」の方はこちら!
Premium
プレミアム
見放題+講師が支える仕組みで実践まで伴走。相談会とコミュニティでつまずきを早期に解消できます。
-
価格
5,500円(税込)/月
-
デジタルブック
記事・動画有料見放題
-
クーポン
ブートキャンプ半額クーポン
トークセッション無料クーポン -
マイアカウント
(学習履歴・保存)あり
-
フレームワーク
グループ相談会あり
-
LINEオープンチャット
コミュニティ参加権あり
\ 今だけ30日間お試し無料! /
「自走学習」に最適!
Standard
スタンダード
旧サイトの見放題プランに相当。相利協創・多主体連携に関するコンテンツを好きなときに閲覧できます。
-
価格
3,300円(税込)/月
-
デジタルブック
記事・動画有料見放題
-
クーポン
ブートキャンプ半額クーポン
トークセッション無料クーポン -
マイアカウント
(学習履歴・保存)あり
-
フレームワーク
グループ相談会なし
-
LINEオープンチャット
コミュニティ参加権なし
「お試し」はこちら!
Starter
スターター
無料記事・動画とマイアカウント機能を体験できます。
-
価格
0円(税込)/月
-
デジタルブック
記事・動画無料のみ
-
クーポン
なし
-
マイアカウント
(学習履歴・保存)あり
-
フレームワーク
グループ相談会なし
-
LINEオープンチャット
コミュニティ参加権なし
INFORMATION お知らせ
2026.02.13
【新機能】ダッシュボードに「マイ道具箱」が登場!
気になるコンテンツを保存して、いつでも見返せる「マイ道具箱」機能がリリースされました。
ユーザー登録(ログイン)するだけで、ダッシュボードから自分専用のコンテンツや記事リストにアクセス可能。
購入したコンテンツもこちらから一覧で見られます。
情報のインプットから実践までを、もっとスムーズに!
2025.12.08
年末年始休業のお知らせ
平素は「協創の道具箱」をご利用いただき、誠にありがとうございます。 勝手ながら、以下の期間を年末年始休業とさせていただきます。
【休業期間】 2025年12月27日(土) ~ 2026年1月4日(日)
休業期間中にいただきましたお問い合わせにつきましては、2026年1月5日(月)より順次対応させていただきます。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
本年中のご愛顧に心より御礼申し上げますとともに、来年も変わらぬお引き立てのほど、よろしくお願い申し上げます。
2025.09.24
Webサイトをリニューアルしました
日頃より、協力アカデミーのWebサイトをご覧いただき、誠にありがとうございます。
本日、当アカデミーの公式サイトを全面的にリニューアルいたしました。
新しいサイトでは、皆様がより快適にご利用いただけるよう、デザインを一新し、スマートフォンやタブレットでも見やすいレイアウトになりました。
講座情報や活動報告なども、より探しやすく、分かりやすい構成へと改善しております。
これからも、皆様にとって有益な情報をたくさんお届けできるよう、内容の充実に努めてまいります。
今後とも協力アカデミーをどうぞよろしくお願い申し上げます。
PARTNERS 協賛団体
SUPPORT US ご寄付のお願い
協創の道具箱の運営は、皆様のご支援によって成り立っています。
いただいたご寄付は、協力アカデミーを通じて、 多主体連携のプロジェクト支援 に役立たせていただきます。
ぜひ、ご寄付のご協力をお願い申し上げます。