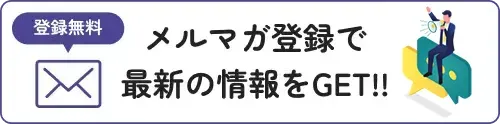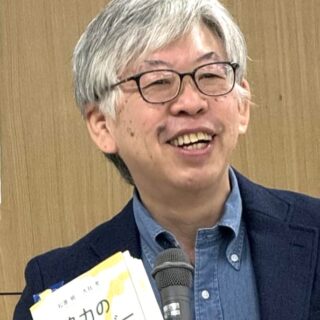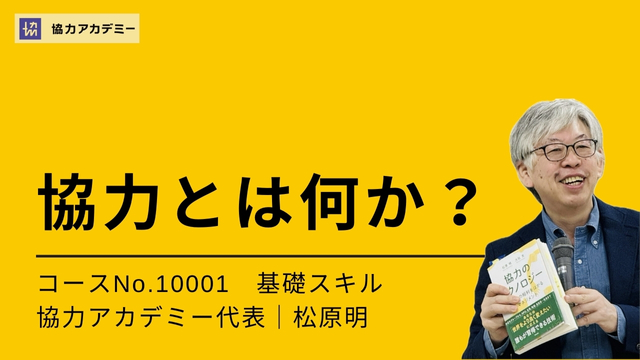2025.10.01
合力の5類型
【社会の仕組みを解き明かす】なぜ人は協力するのか?その答えは「合力の5類型」にあった
私たちは日々、家庭や学校、会社、地域コミュニティなど、様々な組織の中で誰かと力を合わせて生きています。しかし、その「力の合わせ方」に、実はいくつかのパターンがあることをご存知でしょうか?
今回は、協力アカデミーが提唱する「合力の5類型」という非常に興味深いコンセプトをご紹介します。この5つの視点を知ることで、なぜ国家が機能するのか、企業が利益を上げられるのか、そしてNPOが社会課題を解決できるのか、その根本的な仕組みが驚くほどクリアに見えてきます。
あなたも、この記事を読めば、身の回りの組織や社会全体を、これまでとは違った視点で見られるようになるはずです。
そもそも「合力(ごうりょく)」とは?
まず、聞き慣れない「合力(ごうりょく)」という言葉について説明します。
辞書では「人々が力を合わせること」を意味しますが、協力アカデミーでは、これを「人々がどのように力を合わせるか、その方法」という、より深い意味で捉えています。
そして、その力の合わせ方には、大きく分けて5つのタイプがある、というのが今回ご紹介する「合力の5類型」です。
社会を動かす「合力の5類型」
協力アカデミーでは、人々の力の合わせ方を以下の5つに分類しています。
①統治 (とうち)
②交換 (こうかん)
③互恵 (ごけい)
④威信 (いしん)
⑤協力 (きょうりょく)
私たちの社会は、これらの5つの「合力」が複雑に組み合わさって成り立っています。それでは、一つひとつのタイプを、具体的な組織の例とともに詳しく見ていきましょう。
①統治:物理的な力による秩序
これは、一言で言えば「力づく」の合力です。軍事力や警察力といった物理的な力を用いて、「従わなければ大きな不利益が生じる」と示すことで、合意と合力を生み出します。
典型的な組織: 国家
発動条件:自分の物理的な力が、相手を圧倒できること。
国家が法律を制定し、国民に従わせることができるのは、その背景に警察力や軍事力という「統治」の合力が存在しているからです。
②交換:ギブアンドテイクのビジネスモデル
相手が欲しいものを提供することで、見返りにこちらの「してほしいこと」をしてもらう。これが「交換」の合力です。私たちの最も身近にある力の合わせ方かもしれません。
典型的な組織:企業
発動条件:相手が欲しいものを、自分が提供できること。
企業は、顧客が求める商品やサービスを提供して対価(お金)を得ます。また、従業員に対しては給料(お金)を支払うことで、労働力を得ています。まさに「交換」がベースとなって成立している組織です。この合力を発動させるには、相手が何を欲しているのか(ニーズ)を正確に理解することが非常に重要です。
③互恵:「お互い様」という助け合いの精神
「以前助けてもらったから、今度は自分が助けよう」。このような「助け合い」の気持ちから生まれるのが「互恵」の合力です。人間には、誰かから親切にされたら「お返しをしたい」と感じる心理的なメカニズムが備わっていると言われています。
典型的な組織:組合、生活協同組合(生協)など
発動条件:相手が困っているときに、助けてあげること。
生協などが「助け合いの精神」を掲げているように、非営利・共益組織のベースとなる考え方です。相手の中に心理的な「借り」を作ることで、いざという時に力を貸してもらえる関係性を築きます。
④威信:カリスマ性への自発的な追従
「この人についていけば、きっと良いことがあるに違いない」。そう思わせるような「卓越性」に対して、人々が自ら従い、力を貸すのが「威信」の合力です。その卓越性は、知識や技術、財力、家柄、先見性など様々です。
典型的な組織: 宗教の教団、カリスマ的なリーダーが率いる組織
発動条件: 相手が「自ら従いたい」と思うほどの卓越性を示すこと。
例えば、宗教の教団は、神の偉大さや荘厳な建築物などで卓越性を示し、信者は死後の救済といったメリットを期待して力を貸します。また、歴史上の織田信長のようなカリスマも「威信」の一例です。家臣たちは、彼に従うことで将来「一国一城の主になれるかもしれない」という期待を抱き、命を懸けて力を尽くしました。
⑤協力:共通の目標を達成するための結束
ある共通の目的や目標があり、それを達成するために参加者が力を合わせるのが「協力」です。「何かを成し遂げたい」という純粋な思いが原動力となります。
典型的な組織:NPO、市民活動団体、公益法人など
発動条件:協力者双方の目標(相利)が実現できること。
環境保全、子育て支援、地域活性化といった社会的な目的の実現を目指すNPOなどが典型です。この合力を成功させるには、参加者がそれぞれ何を目指しているのか(目標)を深く理解し、共通のゴールを設定することが鍵となります。
社会は「合力」の組み合わせでできている
ここまで5つの類型を見てきましたが、重要なのは、実際の組織や社会は、これらのうちのどれか一つだけで動いているわけではないということです。
例えば、ベースが「交換」である企業でも、カリスマ経営者の「威信」によって従業員の士気が高まったり、プロジェクトチーム内で目標達成に向けた「協力」関係が生まれたりします。
しかし、もし給料の支払いが滞れば、従業員は従わなくなり、チームワークも崩壊するでしょう。このことからも、その組織の基盤(ベース)が「交換」であることがわかります。
私たちは、これら5つの「合力」を無意識のうちに使い分け、組み合わせながら様々な組織を築き、社会を形成しているのです。
まとめ:あなたの周りの「合力」は何ですか?
今回は、社会の仕組みを理解するための新しい視点「合力の5類型」をご紹介しました。
①統治: 物理的な力で従わせる(国家)
②交換: ギブアンドテイク(企業)
③互恵: 助け合いの関係(組合)
④威信:卓越性への追従(宗教、カリスマ)
⑤協力:共通目標の達成(NPO)
このフレームワークを使えば、あなたが所属する組織がどの「合力」をベースにしているのか、そして、より良く機能させるためにはどの「合力」を意識すれば良いのか、そのヒントが見つかるかもしれません。
ぜひ一度、あなたの身の回りの人間関係や組織を「合力の5類型」に当てはめて考えてみてください。きっと新しい発見があるはずです。
ちなみに、次回の動画では、これらの「5類型の作り方」について、さらに深掘りしていくとのこと。そちらも楽しみですね!